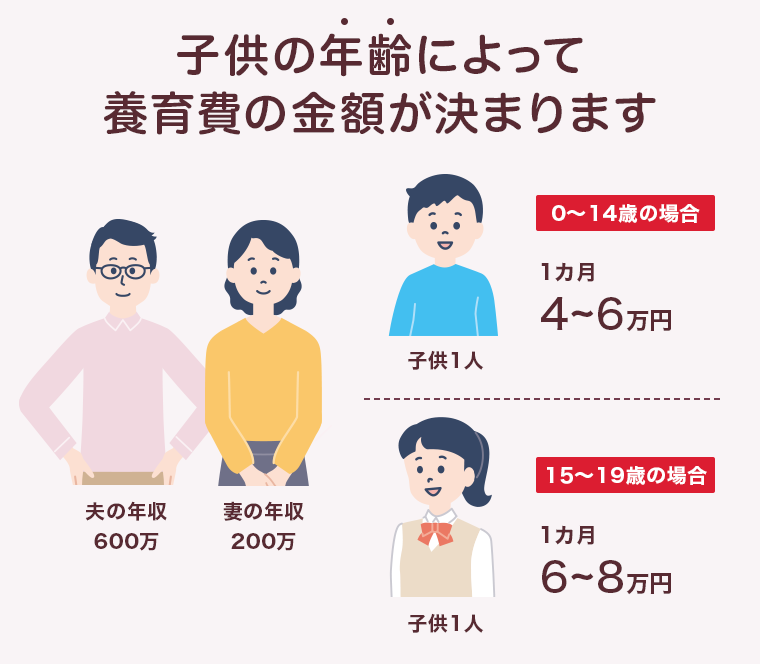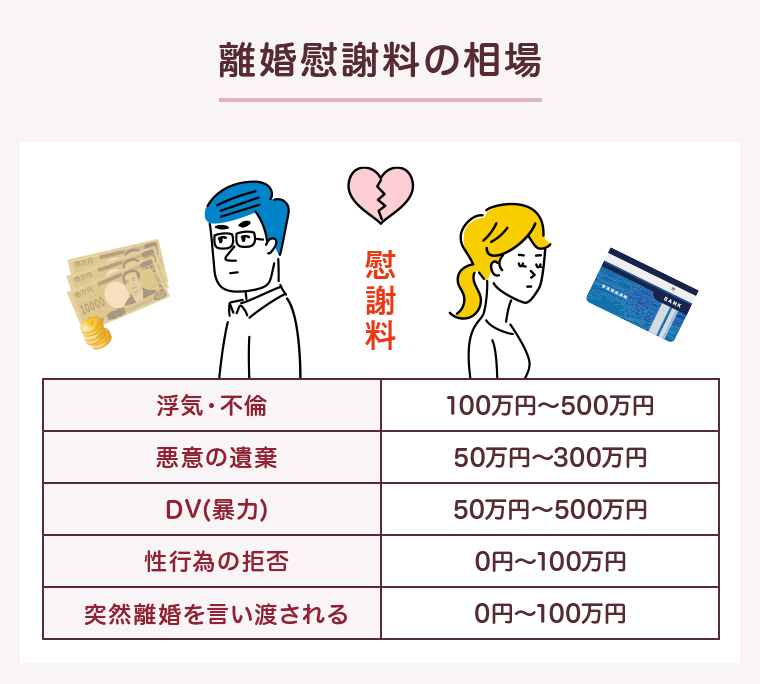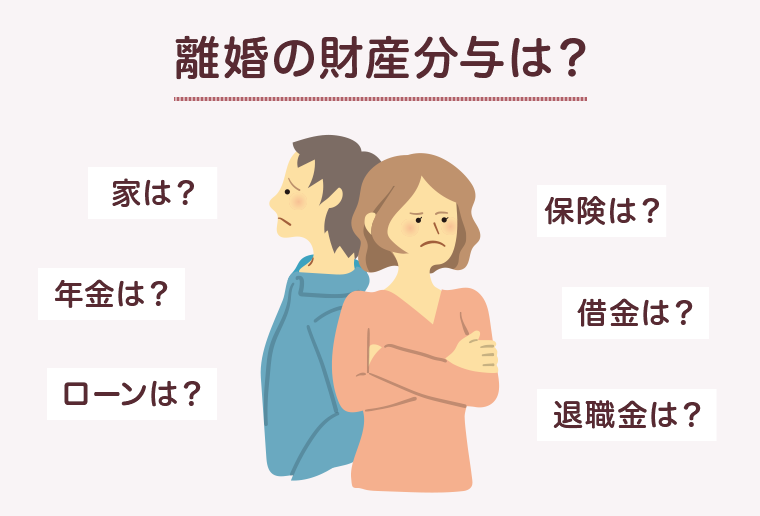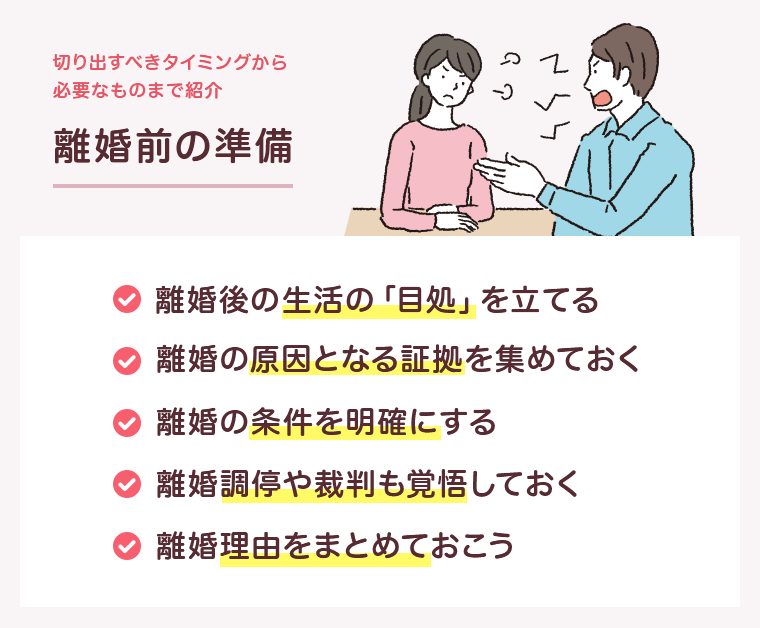父子家庭のための手当や制度一覧|対象になっているならすべて申請を!

離婚や死別により父親がひとりで子どもを育てることになった場合、父子家庭としてさまざまな公的手当や支援制度を利用できます。
一方で、ひとり親をサポートする多くの支援制度は、一般的に母子家庭向けのものと誤解を受けがちで、支援を受けられることを父親が知らないまま困難を抱えるケースが少なくありません。
本記事では、父子家庭が利用可能な子育てをサポートする手当や支援制度を紹介するとともに、実際に支援を受ける際のポイントをわかりやすく解説します。家庭と仕事を両立しながら子育てに向き合う父親の方々は、ぜひ参考にしてください。
目次[非表示]
子育てするうえで大きな力になる、「児童扶養手当」「児童手当」
離婚などの理由で、父か母どちらか一方の養育のみで生活をする児童に対して、地方自治体から「児童扶養手当」が支給されます。また、ひとり親家庭に限らず、全過程を対象に「児童手当」も支給されます。
この二つの手当の恩恵はとても大きく、子どもが二人いる家庭にはトータルで8万円以上支給されるケースもあり、生活するうえで大きな力となります。さらに、東京都など一部の自治体では、児童1人に対して13,500円の「児童育成手当」も支給されます。
児童扶養手当
ひとり親家庭(父子家庭を含む)に対して、地方自治体から子どもの数や収入などに応じた金額の「児童扶養手当」が支給されます。対象となるのは、養育者の所得が一定水準以下の世帯です。子どもが18歳になって高校を卒業する年度まで、継続して受給することができるので、毎月の収入にプラスして家計を考えることができるでしょう。
児童扶養手当の金額は年々上がっていて、全額支給の世帯で43,160円です。さらに子どもの人数によって、2人目には10,190円、3人目には6,110円が加算されます。たとえば3人の子どもを持つ全額支給の世帯では、43,160円+10,190円+6,110円=59,460円が支給されることになります。(2022年3月時点・以下の金額も同様)
児童手当
全家庭を対象とした子どものための手当として、「児童手当」があります。対象となるのは0歳から15歳までの子どもで、中学校修了の年度末まで受けられます。金額は、0歳~3歳未満が一律15,000円、3歳~小学校修了までが10,000円(第1子・第2子)・15,000円(第3子以降)、中学生が一律10,000円です。
| 0歳~3歳未満 | 一律15,000円 |
|---|---|
| 3歳~小学校修了 | 10,000円(第1子・第2子) 15,000円(第3子以降) |
| 中学生 | 一律10,000円 |
たとえば2歳と4歳の子どもを持つ家庭の場合、15,000円+10,000円=25,000円の児童手当を受け取ることができます。シングルマザーで児童扶養手当の全額支給世帯であれば、児童手当25,000円+児童扶養手当59,460円=84,460円を受け取ることができます。
こちらも読まれています母子家庭(シングルマザー)向けの手当・助成制度まとめ。受けられる控除・減免、優先サービスも解説 離婚などによって母子家庭となったときに受けられる支援制度は多数あります。子どもの人数に応じて支給される手当や、一定の条件...この記事を読む
医療費が実質無料になる「医療費支援制度」
ひとり親世帯の保護者や子どもが、病院・診療所で診療を受けた場合に、健康保険の自己負担分を市が助成する制度があります。自治体によっては、1回の診療に対して少額の自己負担を課している場合もありますが、多くの自治体では実質無料で医療を受けることができます。
支援を受けられる期間は自治体によって異なりますが、児童扶養手当を受給している期間中(主に子どもが高校を卒業するまで)は、支援を受けられるケースが多いです。「子どもが風邪をひいた」「虫歯になった」「母が体調を崩した」というときでも、安心して病院に行けるので、ひとり親で子育てをする家庭にとっては本当に助かる制度といえます。
また、入院をした場合も、食事療養標準負担額を助成する自治体もあります。薬の容器代や文書料・差額ベッド代・保険外診療などは助成の対象となりませんが、一部を負担してもらえるだけでも入院時の大きな助けとなるでしょう。
家賃の補助が受けられる「住宅手当」
20歳未満の子どもを持つひとり親家庭で、月額1万円以上の賃貸住宅に住んでいる場合は、家賃の一部を補助してもらえる制度があります。ひとり親家庭にとって、家賃は家計の大きな負担になるので、一部でも補助してもらえることはとても助かります。
補助額は収入によっても違いますが、たとえば東京都東久留米市では月額3,500円、千葉県浦安市では月額15,000円を限度として手当が支給されます。ただし、ひとり親家庭の住宅手当を設けていない自治体もあるので、詳しくは役所のホームページなどで確認しましょう。
教育訓練費の60%を支給する「自立支援訓練給付金」
児童扶養手当を受給している場合、母親(父親)がWebクリエイター能力認定試験やTOEICなど、教育訓練の対象となる講座を修了した際に、費用の60%(上限20万円)を給付する制度があります。詳しくは役所の子育て支援課などに訊ねると良いでしょう。
資格取得まで給付金が受け取れる「高等職業訓練促進給付金」
児童扶養手当を受給している場合、母親(父親)が看護師や介護福祉士の資格を取って自立したいという希望があれば、職業訓練中の全期間(上限3年)にわたって給付金を受け取ることができます。支給額は、市町村民税非課税世帯が月額10万円、課税世帯が月額7万円です。また、訓練が修了した際にも、非課税世帯5万円・課税世帯2万5千円の給付金が支給されます。
ほかにもある手当や制度の一覧
- 保育料負担軽減制度
- 交通費の割引制度
- 上下水道の減免制度
- 粗大ごみ等処理手数料の減免制度
- 所得税・住民税の免除・減免制度
- 国民年金の免除・減免
- 国民健康保険の免除・減免
保育料が半額・または無料になる「保育料負担軽減制度」
国の幼児教育無償化の段階的取組のひとつとして、2016年4月から、ひとり親家庭の保育料の一部を軽減する制度が設けられました。市町村民税の所得割額が一定以下(年収約360万円未満相当)であれば、第1子の保育料が半額・第2子以降の保育料が無料になります。
たとえば市町村民税の所得割額が77,100円以下の世帯で、月額保育料が16,100円だった場合、軽減制度が適用されると第1子の保育料は7,550円、第2子の保育料は無料になります。子どもが複数いる場合は、保育料も家計にとって大きな負担となるので、とても助かる制度ですね。
JR通勤定期の割引が受けられる「交通費の割引制度」
児童扶養手当を受給している世帯は、JRの通勤定期乗車券を3割引で購入できる制度があります。JRだけでなく、市営バスや私鉄などでも割引になるケースがあるので、各交通機関に直接問い合わせてみると良いでしょう。
水道料金が割引になる「上下水道の減免制度」
児童扶養手当を受給している世帯には、水道基本料金や料金の一部が減免される制度があります。ただし、自治体によってはこの制度を設けていない場合もあるので、詳しくは役所のホームページなどで確認しましょう。役所の上下水道問合せ窓口でも聞くことができます。
粗大ごみが無料または割引になる「粗大ごみ等処理手数料の減免制度」
児童扶養手当を受給している世帯は、粗大ごみの処理手数料が免除または減免になる制度があります。この制度も、自治体によっては設けていない場合があるので、詳しく役所のホームページで確認しましょう。
税金が安くなる「所得税・住民税の免除・減免制度」
ひとり親家庭の場合、一定の条件を満たすと、所得税・住民税の減免を受けることができます。詳しくは役所や税務署、企業に勤めている場合は給与の担当者に訊ねましょう。
国民年金の免除・減免を申請できる制度
国民年金は、収入に関係なく月額16,000円以上も支払わされるので、収入の少ないひとり親家庭にとっては大きな負担となります。その場合、国民年金の免除または減免申請をすると、年金の支払額が無料か減額になることがあります。免除額が多い順に、全額免除・4分の3免除・半額免除・2分の1免除といった種類に分かれています。減免できるかどうかは、申請してみないとわかりませんが、まずは役所の国民年金課で相談してみると良いでしょう。
ただし、国民年金の免除申請をした場合は、将来的に受け取る年金額も減ることになります。その辺をよく考えて、国民年金課で詳しく話を聞いたうえで申請することをお勧めします。
国民健康保険の免除・減免を申請できる制度
また、国民健康保険も年々高額になり、生活に困窮している場合は非常に大きな負担となっています。この場合も、国民健康保険の免除または減免申請をすると、健康保険の支払額が無料か減額になることがあります。
国民健康保険の免除に関しては、国民年金のように減額などの問題はありません。役所の国民健康保険課に行き、相談してみると良いでしょう。
父子家庭向け手当・助成を受けるヒント
父子家庭は、母子家庭と比べて制度上の支援は共通であっても、情報へのアクセスや周囲からの支援が限定的になりやすい傾向があります。そのため、制度の存在に気づかないまま経済的・精神的な負担を抱え込んでしまうケースも少なくありません。
以下では、父子家庭の方が手当や助成を適切に受け取るために留意すべきポイントを3つご紹介します。
児童扶養手当は父子家庭も対象と知っておく
児童扶養手当は、離婚や死別などにより、ひとり親として子どもを養育している世帯を対象に支給される公的手当です。「母子家庭のための制度」と誤解されやすい名称ではありますが、実際には父子家庭でも、一定の所得要件等を満たす場合には支給の対象となります。
申請にあたっては、子どもとの同居実態や父親自身の所得状況などが審査されますが、原則として母親が申請した場合と同様の基準で判断されます。自治体の窓口でも「母子家庭を想定した説明」がなされることもあるため、父親自身が積極的に制度の内容を確認し、必要書類を準備して申請することが重要です。
情報収集と孤立を防ぐための相談先を持つ
父子家庭の父親の多くは、日々の仕事と育児を一人で両立することに追われがちです。その結果、行政の支援制度や地域の福祉サービスに関する情報にアクセスできず、制度の存在そのものを知らないまま過ごしてしまう傾向があります。
とりわけ男性の場合、周囲に子育てや生活上の悩みを打ち明けにくく、相談できる相手が限られることが「制度活用の遅れ」につながるケースも見られます。このような場合には、以下のような相談窓口の活用が有効です。
- 自治体の子育て支援課・福祉課
- ひとり親家庭等自立支援センター
- Daddy Support協会・ファザーリング・ジャパンなどの父親支援団体
- 社会福祉協議会、地域包括支援センター
「男性だから大丈夫」と無理をしすぎず、早い段階で支援の選択肢を探ることが、父子家庭の生活安定に直結します。
就労支援や家事・育児支援を積極的に活用する
父子家庭の父親にとって、最大の課題の一つは「仕事と育児の両立」です。
特に、家事や食事の準備、学童の送り迎えといった日常的な負担は、仕事中心の生活スタイルから急に切り替えるには大きな負担を伴います。
こうした事情を考慮し、自治体では次のような支援制度を用意している場合があります。
- 家事代行・育児支援サービスの助成
- 保育所・学童保育の優先利用や延長保育制度
- ひとり親向けの職業訓練給付金・資格取得支援
- 就労支援員によるキャリアカウンセリング
上記に上げたような支援制度やサービスはは父子家庭も対象として設計されているにもかかわらず、男性側の利用率は比較的低いとされています。
社会通念として「父親は働き手」という役割が根強いため、支援を受けることにためらいを感じる方もいますが、生活の安定と子どもの健全な成長のためには、遠慮なく制度を活用すべきです。
まとめ
離婚後に父親が親権を持ち、子どもと共に暮らすことになった場合、父子家庭として受けられる支援や手当は数多く存在します。しかしながら、こうした制度は従来「母子家庭向け」と認識されがちで、男性が活用するにはいくつかのハードルが存在します。
実際には父子家庭の支援制度は、母子家庭と制度上はほぼ同等に設計されています。だからこそ「父子家庭でも公的支援制度は使ってよいもの」「子どものためにも支援を受けることが大切」と認識し、必要なサービスを見極め、積極的に活用していく姿勢が大事です。
今後の生活を安定させ、子どもとの時間を豊かに過ごすためにも、社会の支援資源を正しく理解し、賢く活用することが、父子家庭の自立と安心につながります。
離婚問題に強く評判の良い弁護士事務所を探す
離婚相談離婚問題でお悩みでしょうか?
- 離婚後の生活ついて相談したい
- 慰謝料、養育費を請求したい
- 一方的に離婚を迫られている