みなし相続財産とは?種類・非課税枠など注意点をわかりやすく解説
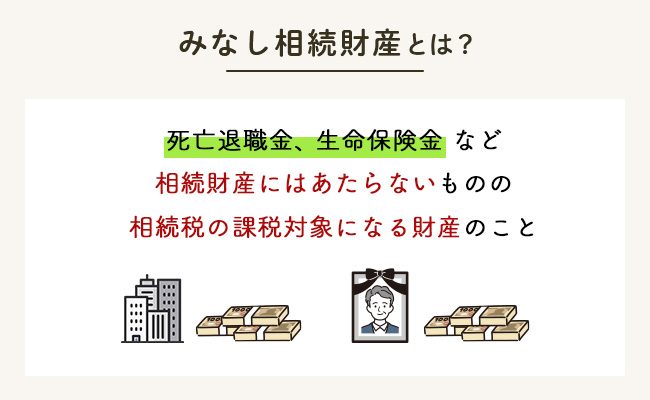
「みなし相続財産」とは、被相続人の死亡により相続人が取得する財産のうち、民法上の相続財産にはあたらないが、税務上は相続税の課税対象とみなされる財産のことです。
みなし相続財産は存命中に所有していた財産ではないため、相続財産にはなりません。ただし、被相続人の死亡によって発生した経済的利益であるため、みなし相続財産として相続税の課税対象とみなされます。
この記事では、みなし相続財産とはどういうものか、その種類や活用できる非課税枠、みなし相続財産に関する注意すべきポイントについてわかりやすく解説していきます。
みなし相続財産とは
「みなし相続財産」とは、被相続人の死亡により相続人が取得する財産のうち、民法上の相続財産にはあたらないが、税務上は相続税の課税対象とみなされる財産のことです。
代表的なみなし相続財産としては、生命保険金や死亡退職金などが挙げられます。
これらは、被相続人が生前中に所有していた財産ではありません。ただし、被相続人の死亡によって新たに発生する財産ではあることから、通常の相続財産と区別して扱われます。
民法・税法における違い
民法上、相続財産は被相続人が死亡時に保有していた財産に限定されます。
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない
民法 第八百九十六条
生命保険の死亡保険金や死亡退職金は、被相続人が亡くなったタイミングで受取人が受け取るお金ですが、被相続人自身が生前に保有していた財産ではありません。そのため、民法上の相続財産には含まれません。
一方、相続税法では死亡保険金・死亡退職金を相続税の課税対象と定めています。
そのほか相続税がかかる財産(みなし相続財産ほか)
次に掲げる財産も相続税法の規定などにより相続税の対象となります。
(1) 死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金など
No.4105 相続税がかかる財産|国税庁
民法上の「遺産」に含まれない保険金や退職金であっても、実質的に被相続人の死亡によって得た経済的利益とみなされ、税務処理では「みなし相続財産」として課税の対象に組み込まれます。
民法と相続税法で解釈が異なりますが、被相続人から受取人への財産移転が存在する実際を考慮し、みなし相続財産として課税が成される仕組みを取っています。
みなし相続財産の種類
実際にみなし相続財産として扱われる財産の種類を、具体的にひとつずつ見ていきましょう。
生命保険金(死亡保険金)
被相続人が契約者・被保険者である場合、被相続人の死亡により支払われる生命保険金は、税法上のみなし相続財産に分類されます。保険契約により受取人が本人以外に指定されている場合でも、受け取る生命保険金は相続税の課税対象です。
ただし、生命保険金の受取人が法定相続人で指定されている場合、生命保険の非課税枠を利用することができます。
生命保険金の非課税枠=500万円x法定相続人の数
受け取った生命保険金の額が非課税枠の範囲内なら、相続税を支払う必要はなくなります。(非課税枠の適用も含めて相続税の申告自体は必要です)
死亡退職金
死亡退職金とは、被相続人が会社への在職中に亡くなった際に発生する、本来退職時に受け取るはずだった退職金のことです。亡くなった社員本人に代わり、遺族に対して支払われます。
この勤務先から支給される死亡退職金も、相続税法上「みなし相続財産」として扱われ、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものが課税対象となります。※なお、死亡後3年を越えて遺族に支給された場合は所得税(一時所得)が適用されます。
みなし相続財産のうち死亡退職金も非課税枠を利用できます。
死亡退職金の非課税枠=500万円x法定相続人の数
死亡退職金の金額が非課税枠の範囲に収まるならば、やはり申告自体は必要となりますが、相続税の支払いは発生しません。
定期金を受け取る権利
被相続人の死亡により、個人年金のように定期的に金銭が支払われる権利を相続人が得た場合、それは定期金として、みなし相続財産に該当します。
たとえば、夫(被相続人)が掛け金を支払い、没後、その妻(配偶者相続人)が年金の支給を受けるケースなどはみなし相続財産とみなされます。
相続税を課税する上での財産評価は、定期金の支払い内容・期間設定などによって異なるため、定期金に対する相続税の対応は税理士や弁護士など専門家に相談するのがおすすめです。
生命保険契約に関する権利(解約返戻金・満期保険金を受け取る権利)
相続人が契約者・被保険者、被相続人が支払者・受取人となっていた保険契約がある場合、その解約返戻金・満期保険金を受け取る権利は相続人に引き継がれ、みなし相続財産として課税対象となります。
これはたとえば「親の費用負担で子の保険を契約していた、万一の場合の受取人は親になっていたケース」を指します。このケースで親が亡くなった場合、子は自ら支払者・受取人となり自分にかけられた保険契約をそのまま引き継ぐ、あるいは解約することになります。引き継ぐでも解約でも、いずれの場合でも、親から子へ解約返戻金・満期保険金が引き継がれるるため、実質的な受益権の移転とみなされ、みなし相続財産にカウントされます。
こうしたケースは上記の親子間の他、夫婦間・祖父母と孫などによるケースも考えられます
債務免除
遺言により被相続人から債務(借金)の免除を受けた場合、免除された金額はそのまま経済的利益とみなされ、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
たとえば、相続人が被相続人から借りていた3000万円の借金を遺言で帳消しにしてもらった場合、帳消しとなった借金分3000万円の利益を得たものとみなされ、みなし相続財産となります。
また、被相続人からの借金全額免除以外にも、遺言により本来の時価より著しく低い価格で財産を取得した場合も、支払い免除された時価と支払額の差額はみなし相続財産として課税を受けます。
たとえば時価7000万円の土地を1000万円で譲り受けた場合、土地の1000万円とともに、時価との差額6000万円も相続税の課税対象となります。
被相続人の死亡前7年以内に贈与を受けた財産
相続開始前7年以内に生前贈与された財産は相続税の課税対象となります。(みなし相続財産ではなく、正式な相続財産として扱われます。)
従来、この相続税の課税対象となる加算期間は相続開始前3年でした。被相続人が死亡する3年以上前の生前贈与は相続税の対象とならないことから、年間110万円の暦年贈与で生前贈与を進めていく節税対策が多々活用されていました。
これが2024年(令和6年)1月1日以降の贈与からは死亡前7年に延長され、贈与税の非課税枠を用いた生前贈与による節税は実施しづらくなりました。
生前贈与における課税対象の加算期間については、下記の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。
こちらも読まれています生前贈与にかかる相続税は亡くなる7年前の分まで。加算対象となる贈与の考え方、節税方法と注意点 2023年の税制改正により、生前贈与の相続税加算期間がこれまでの3年から7年に延長されました。これにより、相続税の節税対...この記事を読む
みなし相続財産(生命保険金・死亡退職金)の非課税枠
生命保険金や死亡退職金については、相続税法において非課税枠が設定されています。
具体的には 500万円 × 法定相続人の数 が非課税枠として認められています。
たとえば生命保険金が2000万円、相続人が配偶者1人・子ども2人の計3人だった場合、生命保険金のうち非課税枠1500万円を越えた部分、つまり500万円が課税対象となります。
生命保険金 2000万円 – 非課税枠(500万円 x 法定相続人 3人)=課税対象額 500万円
相続放棄した相続人も法定相続人にカウントされる
非課税枠を計算する際は、法定相続人の数には相続放棄した人も含めてカウントして計算します。
相続放棄した人は、相続人でなくなることで相続財産を受け取る権利を失いますが、税額計算上は相続人がいるものとして計算を行います
生命保険は契約上の受取人に対し、死亡退職金は会社の就業規則等に基づいて決定された受取人に対して支払われます。
契約・規約上のルールに基づき処理され、相続放棄の有無が支払いに影響することはありません。
法定相続人以外の人・相続放棄した人は非課税枠の対象外
- 法定相続人以外が受け取った場合
- 相続放棄した人が受け取った場合
ただし、法定相続人以外あるいは相続放棄した人が受け取った場合、非課税枠の適用対象からは除かれ、生命保険金・死亡退職金として受け取った全額に対して相続税が課税されます。
遺産分割の兼ね合い等で相続放棄した人が生命保険・死亡保険金を受け取る場合、他の相続人に比べて受取額は目減りすることになります。
思わぬ課税負担が生じる可能性があるため、遺産分割協議を行う際、相続放棄をするかどうかは慎重な判断が必要です。
こちらも読まれています相続放棄とは?するとどうなる?手続きの流れや注意点について解説 相続放棄をすると、借金も資産も相続しません。明らかに債務超過になっている場合や遺産分割トラブルに関わりたくない場合に利用...この記事を読む
みなし相続財産の注意点
その他、みなし相続財産に関する注意点を見ていきましょう。
みなし相続財産は遺産分割の対象外
生命保険金・死亡退職金などのみなし相続財産は遺産分割の対象外です。みなし相続財産は契約等により定められた受取人の固有財産として扱われます。
そのため、基本的には生命保険金や死亡退職金を相続人間で分配する必要はありません。
ただし、生命保険金や死亡退職金の受け取り金額を考慮して遺産分割の配分が行われるケースも少なくありません。
相続人間で公平に遺産分配しようとした際、生命保険金などを誰が受け取ったかが原因でトラブルになることもあります。
そうならないよう、事前にみなし相続財産のこともふくめて、相続人間でしっかり話し合っておくことが重要です。
生命保険は保険金の受取人に注意
保険金の契約者・被保険者・受取人が誰に設定されているかは、税務面で大きな意味を持ちます。
それぞれが誰になっているかによって、かかってくる税金の種類が異なってくるためです。
| 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 | |
|---|---|---|---|---|
| 契約者と被保険者が同一 | A | A | B | 相続税 |
| 契約者と受取人が同一 | A | B | A | 所得税 |
| 契約者、被保険者、受取人がすべて別 | A | B | C | 贈与税 |
相続税が適用されるのは契約者と被保険者が同一なケースで、その他、所得税や贈与税が適用されるケースもあります。
どの税金の適用にするのが最適かは、生命保険金以外の通常の相続財産の内容もふまえた判断が必要です。
事前に、被相続人が契約・加入している保険の契約内容を確認しておくことは、相続発生後のトラブル予防や税務上の不利益の回避につながります。
法定相続人以外の場合は相続税2割加算の対象に
また、保険金の受取人が法定相続人以外の第三者である場合、相続税は通常より2割多く課税されます。
該当するケースとしては、たとえば相続放棄した相続人が受取人となった場合、内縁関係の相手や知人・友人が受取人である場合などが挙げられます。
被相続人(契約者)が意図して指定していたとしても、結果として受取人に指定された方を困惑させたり、受取人に指定されなかった法定相続人との間でトラブルとなる可能性も考えられます。
法定相続人以外が受け取る保険契約を利用する場合は、遺言やエンディングノートなどで被相続人の意思を明示しておくことをおすすめします。
節税に使える生命保険の非課税枠
生命保険の非課税枠は、適切に活用すれば相続税の節税手段として有効です。
上述の通り、契約者・被保険者・受取人の組み合わせによって課税関係が変わるため、相続対策として保険契約を見直す際には、税理士や保険の専門家と相談しながら進めるのが望ましいでしょう。
特に相続税の基礎控除を超える遺産がある場合には、保険を活用した対策が功を奏するケースもあります。
まとめ
みなし相続財産は、民法上の相続財産(被相続人が生前保有した財産)ではないものの、被相続人が死亡することではじめて発生する経済的利益のことを指します。みなし相続財産は相続財産ではないため遺産分割の対象外ですが、相続税の課税対象となります。ただし、代表的なみなし相続財産である生命保険金や死亡退職金には、法定相続人の数に応じた非課税枠が認められており、うまく活用することで相続税の節税に活用することが可能です。
ただし、受取人が相続人以外である場合・相続放棄した方が保険金を受取る場合など、一定の条件の場合、相続税の2割加算の対象となり、税額が増える可能性があります。
あらかじめ保険の契約内容をよく理解し、他の相続財産や相続人の状況をふまえた最適な相続時の計画立てを行うことが、相続人間あるいは相続人と受取人間の無用なトラブル、重い税負担を避ける第一歩になります。
みなし相続財産があり、どう対応すべきかわからない、非課税枠を用いて適切な形で節税を行いたい方は、弁護士や税理士など相続の専門家に相談することをおすすめします。
遺産相続に強く評判の良い弁護士事務所を探す
遺産相続この記事が役に立ったら
いいね!をお願いします
最新情報をお届けします
相続問題で悩みを抱えていませんか
- 相手がすでに弁護士に依頼している
- 遺産分割の話し合いがまとまらない
- 遺産を使い込まれているがどうすれば?