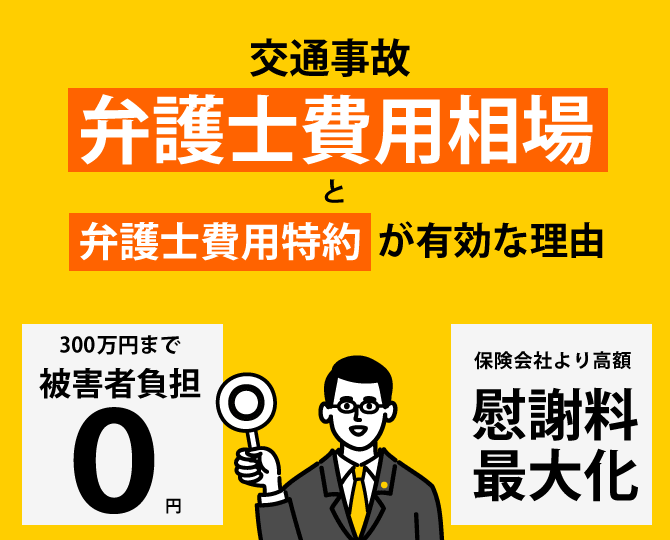民事裁判とは?交通事故で裁判まで進んだ場合
- 監修記事
-

佐藤 學(元裁判官、元公証人、元法科大学院教授)

交通事故の損害賠償問題は、民事裁判の場で争われます。簡易裁判所または地方裁判所に訴えを起こし「裁判」は始まります。一方、「裁判」の途中で、裁判所から和解を勧められる場合もあります。裁判の期間や費用が勘案され、被害者側が和解に応じるケースが多いとされます。
目次[非表示]
交通事故の損害賠償問題は民事裁判の場で争われ決着
双方が合意すれば示談または和解の道もある
交通事故の損害賠償交渉は、まず当事者同士の話し合いの「示談交渉」、合意に至らない場合はADR機関での「和解あっ旋」または裁判所での「調停」へと進みます。これらの過程を経ても合意に至らない場合は、「裁判」において最終的な決着をつけることになります。また、「裁判」の過程で、双方が合意すれば、和解という解決策もあります。
交通事故の損害賠償問題で「裁判」にまで進むことは少なく、ほとんどの場合は「示談」でなんらかの合意を見るケースが多いのが実情です。
しかし大きな事故で多額の損害賠償金を請求する場合、後遺障害で賠償金額が高額となる場合、また交渉の相手方に誠意が見られず交渉が進まない場合などにおいて、「裁判」は被害者にとって頼りになる解決方法です。
交通事故の損害賠償で裁判になるケース
一般的な「裁判」として知られているのは、刑事裁判です。
警察官が犯罪を捜査し、犯人だと疑われる人を検察官に送致し、検察官が事件について必要な捜査を遂げた後、的確な証拠に基づき有罪判決が得られる高度の見込みがあれば、公訴の提起(起訴とも言われ、略式命令請求と公判請求があります)をして、刑事手続に基づく裁判となります。
しかし、交通事故においては、すべての事故について起訴されるわけではなく、起訴されたとしても、その多くは略式命令請求により略式手続きで終わり、公判請求により公判の裁判となるのは
- ひき逃げ、飲酒運転、過度なスピード違反などに伴う悪質・危険な死傷事故
- 過失の程度が大きく、被害結果も重大である死傷事故
などの場合に限られるのが現状です。
交通事故の損害賠償問題は主に民事裁判で争われる
交通事故に関する事件が刑事裁判で争点となるのは、被告人となる加害者が有罪か無罪か、そして量刑が中心になり、被害者への賠償問題は争われません。
刑事裁判における刑罰は、懲役、禁錮または罰金となりますが、直接被害者の利益となることはなく、裁判所が加害者に罰を与えることになるだけです。
被害者が受けるべき損害賠償の問題は、主に民事裁判で争われるのです。
民事裁判は誰でも起こせる
刑事裁判の場合、被告人(交通事故では加害者)を起訴できるのは検察官だけです。
民事裁判は、日常生活で起こる法律上の争いを解決する場であり、刑事裁判とは違い誰でも訴えを起こすことができるのが特徴です。すでに成人であればひとりで、未成年であっても法定代理人が代わりに、「裁判」を起こすことが可能です。
こちらも読まれています本人訴訟とは~個人で起こす交通事故の民事裁判 裁判を起こすためには必ずしも弁護士を雇う必要はない。特に交通事故の少額訴訟では、この「本人訴訟」が弁護士費用を節約するた...この記事を読む
民事裁判の手続きは個人でもできる
「裁判」を起こすとなると、手続きが分からない、また自分だけで法廷に立って良いのかという不安などから、弁護士に依頼することが必須だと考えている人が多いのではないでしょうか。
弁護士に依頼しなくても訴訟を起こすこと自体は可能
弁護士を雇い、難しい書類を山ほど作って、裁判の日には仕事を休んで…、と「裁判」が続いている間は、「裁判」中心の生活になってしまうのではないかと心配する人もいるかもしれません。
実際には、民事裁判においては弁護士に依頼しなくても訴訟を起こし「裁判」の場で争うことができるのです。
訴状をはじめ、「裁判」に必要な書類なども、書き方を分かりやすく解説した書籍やインターネットサイトがありますので、それらを見本にすれば良いのです。
民事裁判に出頭義務はある?
また、民事裁判では、刑事裁判とは違い、訴訟代理人(弁護士)がいれば、当事者(原告であれ、被告であれ)が毎回の口頭弁論期日に出頭する義務はありません。
ただし、自分ひとりで訴訟をしている場合には、裁判所からの呼出しに応じない場合、直ちに不利益が生じる可能性があります。
欠席のまま判決を出されるケースも
被告が、訴状と第1回口頭弁論期日の呼出状が送達されたのに、答弁書等を提出することなく、第1回口頭弁論期日を欠席すると、裁判所は、被告が訴状に記載されていることを明らかに争わないものとみなし(民訴法159条1項。「擬制自白」と呼ばれています)、原告の請求を認容するという欠席判決を出すことが多いのです。
被告が、原告の請求権を争う場合には、その旨を記載した答弁書を提出しないと、上記のとおり欠席判決という不利益を受けることになります。もっとも、第1回口頭弁論期日は、被告の都合を聞くことなく一方的に定められることが多いため、答弁書を提出しておけば、最初の口頭弁論期日に限っては、答弁書に記載されている主張を陳述したと擬制されます(民訴法158条)。
欠席のまま判決を出されるケースも
また、当事者が期日に出頭しないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができます(民訴法166条)。さらに、当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭しない場合において、1月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなされ、また、当事者双方が、連続して2回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭しないときも、訴えの取下げがあったものとみなされます(民訴法263条)。
交通事故の「民事裁判」の場合は、「示談」や「調停」がもつれて決裂し、「裁判」にまで突入しているような複雑な揉め事ですから、弁護士を依頼することがベストですが、基本的には、民事裁判は誰でも訴訟を起こせ、個人でも争えるということを覚えておきましょう。
また、いざ実際に民事裁判という際には、法廷に出頭しない場合に生ずる上記のような不利益も理解しておく必要があります。
民事裁判における訴訟手続の流れ
民事裁判は、訴えの提起によってスタートします。
訴えを起こした方を原告、訴えられた方が被告と呼ばれ、基本的には被害者が原告、加害者が被告となります。
民事裁判の訴えは誰でもできますので、稀なケースですが、原告と被告が逆になることもあり得ます。
損害賠償金額で裁判所が違う
民事裁判では、求める訴額(損害賠償の金額)によって、訴えを起こす裁判所が違います。
訴額が140万円以下の場合は簡易裁判所、それを超える場合は地方裁判所となります。
訴えを起こすのは、
- 被害者の住所地(民訴法5条1号、民法484条)
- 加害者の住所地(民訴法4条1項2項)
- 交通事故が発生した地(民訴法5条9号)
いずれかを管轄する裁判所です。
裁判所の所在地は裁判所ホームページで確認が可能です。
訴額が60万円以下の場合は少額訴訟で
訴額が60万円以下の訴訟は、簡易裁判所において少額訴訟として取り扱われます。
簡易裁判所には、定型訴状用紙や定型答弁書用紙が備え付けられていますので、誰でも簡単に訴状や答弁書を作成することができるようになっています。法律の知識がなくても、誰でも自分でできる簡便な裁判手続です。
「裁判」の当事者に、なるべく負担の少ない裁判手続で紛争の解決を目的とする制度で、原則として1回の期日で審理を終えるものです。
民事裁判ではラウンドテーブル法廷という、裁判官と原告、被告がひとつのテーブルを囲んで「裁判」を行うことがありますが、少額訴訟ではこの方式がよく用いられるようです。
少額訴訟は1日で判決が出る裁判
また、少額訴訟では、通常の訴訟とは違い、1回の期日で、証拠書類を取り調べ、本人尋問を行って審理を終え、直ちに判決が言い渡されます。
提出できる証拠や証人は審理の日に調べられるものに限定され、場合によっては十分に審理を尽くしたとは言えないケースが発生することが考えられます。
判決では、被告(加害者)の事情によって、分割払いや一定期間支払い猶予を言い渡すこともできます。
また、少額訴訟判決に対する控訴ができず、判決を言い渡した裁判所に対する異議申立てに限られるなど、不服申立て方法が限定されています。
少額訴訟手続でも、裁判官の勧告により、和解で解決することもできます。
少額訴訟に異議がある場合は通常訴訟での裁判に
ただし、被告(相手方)に、少額訴訟手続で処理することに異議があれば、通常の訴訟手続で裁判がなされることになりますので、注意が必要です。
民事裁判の途中で和解となる場合も
民事裁判においては、交通事故の当事者双方が原告と被告に分かれ、お互いの言い分を主張し合い、最終的には裁判所の言い渡す判決によって決着がつけられますが、訴訟の途中で和解によって解決されるケースも多く見られます。
強制執行が可能な和解
交通事故の「裁判」を続けていく中で、裁判所が和解を勧めることがあります。
現在の民事訴訟にとって、裁判上の和解(民訴法89条、267条)の果たす役割は、非常に大きいのです。
裁判所が和解案を作成しますが、基本的には判決と同じ内容であることが多く、裁判上の和解を記載した裁判所書記官が作成する和解調書には、確定判決と同一の効力が認められるため(民訴法267条)、執行力のある債務名義(民事執行法22条7号)になります。
「裁判」を起こしているのに、和解に応じることは難しいと考えるかもしれませんが、手続きが早く済むため、裁判上の和解で決着するケースも多いのが実情です。
判決に不服がある場合は上訴が可能
民事裁判において、裁判所によって言い渡された判決には、被告は従う義務はありません。
もし、言い渡された判決に不服がある場合は、上級裁判所に控訴、または上告することができます。
上訴とは?
控訴と上告を合わせて、上訴といいます。
控訴とは、第一審裁判所の判決に対する不服申立て、上告とは、第二審裁判所の判決に対する不服申立てを指します。
上訴は、審理のやり直しを求める手続きとなりますが、判決が言い渡されてから一定期間が過ぎてしまうと、その判決は確定しますので、被告は必ずこれに従わなければなりません。
被告の支払い能力を調査すること
そもそも「裁判」を起こす時にも同じことが言えますが、いくら「裁判」で勝訴判決を得ても、加害者(被告)に支払い能力がなければ、確定判決の債務名義により強制執行の申立てをし、差押等の手続が行われても、被害者(原告)は支払いを受けることはできません。
加害者の任意保険加入の有無やその内容、預金や給与などの財産調査を行った上で、訴訟するかどうかを判断する必要があります。
民事裁判には、各種の費用がかかる
刑事裁判と民事裁判には、費用面の違いもあります。
刑事裁判の場合、被害者が直接「裁判」を起こすわけではありませんので、加害者が起訴されても被害者には費用はかかりません。
逆に、証人として出頭して証言すれば、旅費、日当及び宿泊料が裁判所から支払われます。
一方、民事裁判を起こすには、費用が必要です。
民事裁判では、自ら「裁判」を起こすわけですから、弁護士に委任しなくても、「裁判」をする費用は負担しなければならないのです。
なお、訴訟で請求する場合、損害額から過失相殺・損益相殺等の諸控除をした後の金額に、10%の弁護士費用を加算して請求するのが一般的です。
裁判例では、認容額の10%程度が事故と相当因果関係のある弁護士費用として認容されています。
こちらも読まれています「民事裁判」開始の手続きと費用~交通事故の民事裁判① 民事裁判と刑事裁判の違いに、費用がかかるという点がある。民事裁判では原告がまず裁判費用を支払う。刑事裁判では国が原告とな...この記事を読む
交通事故に強い【おすすめ】の弁護士に相談
交通事故一人で悩まずご相談を
- 保険会社の慰謝料提示額に納得がいかない
- 交通事故を起こした相手や保険会社とのやりとりに疲れた
- 交通事故が原因のケガ治療を相談したい