遺産相続争い~遺産分割でもめるパターンと相続トラブルの対策方法

遺産相続をするときには、相続争いが起こってしまうことが非常に多いですが、実際にはどんな揉め事が起こりやすいのでしょうか?トラブルの予防方法や、問題が起こってしまった場合の対処方法についても押さえておきましょう。今回は、遺産分割でもめるパターンと対策方法について、解説します。
目次[非表示]
遺産相続トラブルは急増している?

「遺産相続ではトラブルが多い」
世間一般でよくそのようなことを耳にするけれど、「自分には関係ないわ」と思っている人が多いのではないでしょうか?
「相続トラブルなんて、一部のお金持ちの話でしょ?」そう考えている人も多いと思います。しかし、このような考えは間違いです。
遺産相続トラブルの多くは、中流家庭で起こっている
遺産相続トラブルは、多くが遺産総額5,000万円以下の一般中流家庭で起こっています。また、相続トラブルの件数は、近年増加傾向にあります。
裁判所の司法統計によると、平成14年において、遺産分割調停や審判の事件数は11,223件でしたが、平成24年には15,286件となっていて、件数は10年間で約1.4倍にもなっています。ま
た、遺産分割事件が起こった中での遺産の額は、1,000万円以下の件が約3割、1,000万円超5,000万円以下の件が約4.4割となっており、合計7割以上の件では遺産総額が5,000万円以下なのです。むしろ、1億円を超えるような資産家の家での遺産相続事件の方が少ないことがわかります。
このように、遺産相続トラブルは実際には普通の中流家庭で非常に多く起こっているのであり、決して他人事ではありません。
こちらも読まれています遺産相続とは? 手続きの流れと期限など押さえておきたい5つのポイント 遺産相続をするときに必要な手続きは多岐に渡り、非常に複雑です。財産などをめぐって相続人同士でのトラブルも起こりがちで、相...この記事を読む
仲が良くても遺産争いは起こる
ここまで聞いても「うちは兄弟みんな仲がいいからトラブルになんてならない」「子どもたちは、きっと譲り合うと思う」などと考えて、やっぱり遺産トラブルと関係がないと思う人がいるでしょう。しかし、このような考え方も甘いです。
家庭裁判所で遺産分割調停を起こしたり、相続人間で熾烈な争いを繰り広げたりしているケースの多くは、もともとが仲の良かった兄弟です。
普通に親族付き合いをして、電話やメールをしたり一緒に遊びに行ったり旅行に行ったりしていた兄弟が、相続トラブルをきっかけに、お互いが心底憎み合い、一生絶縁状態になることも非常に多いです。しかも、そのような兄弟間の相続トラブルは、多くが親が亡くなってから起こります。
親は何も知らずに亡くなるわけですが、その後子どもたちが酷い相続トラブルを繰り広げて疲弊しているわけです。このような事例を見ると、「親はきっと天国で泣いているだろう…」と思い、悲しい気持ちになるものです。そんな残念な結果にならないよう、生前からしっかり遺産相続対策をしておかなければなりません。ここまで読んで、「相続対策しなくちゃ」という気持ちになっていただけましたでしょうか?
遺産相続でもめる、トラブルになるデメリット

遺産相続問題でトラブルが発生しても、どんな問題が起こるのかわからない人もいるかもしれないので、以下では具体的にどんなデメリットがあるのか見てみましょう。
遺産分割が長びく
まず、相続でもめると、遺産分割をすることができません。遺産分割協議で合意ができないと、家庭裁判所で遺産分割調停をしなければなりません。調停でも解決ができないなら、遺産分割審判が必要になります。このように手続きがどんどん長びいていくと、相続が開始してから3年以上経っても延々と相続争いを繰り広げている、ということも普通に起こります。
このような事例でも、もめている当人自身は好きで争っているのではなく「一刻も早く解決したい」と考えているものです。それでも、お互いが「絶対譲りたくない」と考えるので、実際には解決することはできず、時間が経っていきます。
こちらも読まれています遺産分割とは?分割方法と手続きの流れについて解説 遺産分割は、家族や親族が亡くなると発生します。故人の遺産と意志を引き継ぐ大事な手続きであると同時に、時には相続人の間で大...この記事を読む
相続人や孫が疲弊する
遺産相続トラブルが起こると、相続人は非常に疲弊します。そもそも争いごとを抱えているだけでもストレスがたまりますが、遺産問題では相手に対して感情的になるので、精神的な負担が大きくなりやすいです。
遺産相続トラブルを起こしている人の多くは、高齢者
今の日本は高齢化社会なので、被相続人自身が80歳以上になるため、相続人が60代や70代になることもあるのです。もともと体力もないところに持ってきて熾烈な相続争いを繰り広げるので、その負担は想像に難くないはずです。
しかも、こうした高齢者が相続人になるとき、子ども(被相続人の孫)に手伝わせることもあります。たとえば、孫が相続人の代わりに弁護士に相談に行ったり遺産分割調停の手続きをしたりします。孫は現役世代ですから、仕事もしながら親の相続問題にかかわらないといけなくなり、やはり大きな負担がかかってしまいます。
このようなことは、すんなり遺産分割ができたらすべて不要なことなので、相続問題はスムーズに解決する必要があります。
相続税の控除を受けられない
遺産分割をスムーズに進められないと、相続税の控除を受けられなくなるおそれがあります。相続税には、配偶者控除や小規模宅地の特例などの各種の控除制度がありますが、これらの制度の適用を受けるためには、原則として相続税支払期限である相続開始後10ヶ月以内に遺産分割協議書を添えて相続税の申告をしなければなりません。
それができない場合、相続税の申告期限後3年以内であれば遺産分割協議を成立させて控除を受けることも可能ですが、それを超えてくると、控除を受けられなくなる可能性が高くなります。
こちらも読まれています遺産相続の時に相続税控除の恩恵を受けられるのはどんな人? 相続税が高額となるため相続を放棄するケースも往々にしてありますが、ある特定の属性を持った相続人には、様々な相続税の控除制...この記事を読む
このように、遺産争いが長引いてくると、相続税の控除を受けられなくなって、かかる相続税の金額が大きく上がり、全体として大きな損失になってしまいます。
相続財産の活用ができない
遺産相続トラブルが長びくと、せっかく相続した財産の活用をすることができないことも問題です。たとえば、預貯金があっても出金ができず、宙に浮いたままになります。株券や投資信託などのケースでも同じです。不動産がある場合、本来なら賃貸に出して収益を得たり売却によってお金に換えたりしたら有効に活用できますが、そういったことも難しくなります。
ただ、不動産は何の活用もしていなくても、毎年固定資産税だけは確実にかかってしまいますし、管理コストもかかるので、相続争いをしていて放置しているだけ、損失になってしまいます。
事業承継が関連するケースでは、相続争いが起こってスムーズに事業承継できないことにより、会社の経営が停滞してしまうケースもあります。
こちらも読まれています親族内承継~ご子息など家族への事業承継はリスクを理解して 事業承継の中でも、子どもなどに会社を継がせる「親族内承継」は最も頻繁に利用される方法です。ただ、親族内承継には時間がかか...この記事を読む
兄弟や親戚が絶縁状態になる
諫相続トラブルが起こると、当事者同士は酷く憎み合います。このことは、もともと仲がよかったかどうかと無関係な問題です。親が生きているときには、トラブルの片鱗も見せなかったような子どもたちが、親の死亡後には人が変わったように憎み合い、ときにはお互いを刑事告訴することすらあります。
当然、兄弟や親戚は絶縁状態になってしまいますし、その後の法事などの祭祀もスムーズに行うことができません。
こちらも読まれています遺言の内容に納得がいかない場合でも絶対に従わなくてはいけないのか?ケース別に解説 遺言書に「全財産を寄付する」「全財産を愛人に渡す」と書いてある場合や、兄弟で不公平な場合など遺産分割で納得できない場合は...この記事を読む
遺産相続対策は弁護士に相談しましょう
以上のように、相続争いが起こると、いろいろなデメリットが多すぎるので、やはり事前に予防する必要が高いです。遺産相続対策をするときには、弁護士に相談すると役に立ちます。弁護士であれば、効果的な遺言書作成方法や遺産トラブルの予防方法をアドバイスしてくれますし、実際にトラブルが起こった後でも、最もスムーズな解決方法を提案してくれるからです。
困ったときや疑問がある場合、まずは一度、遺産問題に強い弁護士に相談してみましょう。
遺産相続に強く評判の良い弁護士事務所を探す
遺産相続遺産相続トラブルには「もめるパターン」がある
それでは、遺産相続トラブルはどのようにして防いだらよいのでしょうか?実は、遺産相続で争いが起こる場合「パターン」があります。トラブルが起こりやすい事例を押さえておけば、そうならないように対処できます。そこで、具体的にどんなトラブルのパターンがあるのか、以下で見てみましょう。
遺産の中に不動産がある

不動産に関連するトラブルは避けにくい
まず、遺産の中に不動産があると、遺産トラブルが起こりやすいです。
そして、実際に遺産の中に不動産が含まれていることは非常に多いです。国税庁の平成24年度のデータによると、遺産の中で、土地は45%、家屋は5%程度となっており、不動産が遺産の半分以上を占めているのです。また、こうした不動産にまつわるトラブルの多くは「たった1つの実家の土地建物」です。特に投資用に不動産がたくさんあるわけではなくても、相続トラブルは起こります。
親の立場からしてみたら、「将来の相続トラブルを避けるため、今住んでいる実家を売ろう」、などと考えることは通常ありません。ということは、「不動産に関連した遺産トラブルを避ける」ことは、とても難しいということになります。そこで、遺産の中に不動産がある場合のトラブル要因と対処方法を把握しておく必要があります。以下で、不動産を相続する際にトラブルになったAさんのケースを見てみましょう。
Aさんのケース
Aさん(50代 女性)は3人兄弟の末の妹で、上に兄2人がいます。親が亡くなったので、兄弟3人で相続をすることになりました。遺産はそう多くなく、実家の土地建物とその他の預貯金が少しあるだけでした。長男は親と同居していたのですが、「僕が家を継ぐから、家は全部僕がもらう」と言い出しました。
次男とAさんは驚いて「法定相続分があるからそれはおかしい」と言いましたが、長男は聞き入れません。次男は「実家は古いから、売却して現金で分けるのが最も公平」と言っています。Aさん自身は、別に売却しなくてもいいので、長男が代償金を払ってくれたらいいと思っています。そこでAさんが、不動産の評価書を取得すると、3,000万円でした。
Aさんがその評価書を持って兄のところに持っていき、3分の1である「1000万円を支払って」と言うと、兄は逆上して、「そんなに高いはずないだろ!」と言い出して、評価額は「2000万円だ」と言いだし、相続税路線価の価格や他の不動産業者で査定し金額を持ち出して争ってきました。
このように、三者三様の主張をするのでまったくまとまらず、結局遺産分割の調停、審判を経て、家は最終的に競売にかかりました。家は安い金額でしか売れず、長男も次男もAさんも疲れ果てただけで、手元にはほんの少しの現金が残っただけでした。しかも、兄弟3人の親類付き合いは完全になくなってしまいました。
なぜ遺産相続でもめるのか?
不動産の分割方法でもめる
このように、不動産があるともめてしまうのはどうしてなのでしょうか?1つには、不動産の分け方が複雑なことがあります。現金や預貯金などであれば、単純に法定相続分に応じて分けたら済むのでとても簡単ですが、不動産は固まりの財産ですから、法定相続分に応じて分割することができません。
そうなると、1人の相続人が相続をすることが考えられますが(現物分割)、そうなると他の相続人との間で不公平になります。そこで、不動産を取得する相続人が他の相続人に代償金を支払う方法が考えられますが(代償分割)、この方法は、不動産を取得する相続人に支払い能力がある場合でしか利用できません。
また、もう1つの方法は、不動産を売却して現金で分ける方法ですが、この方法だと不動産という資産が失われてしまうため、反対意見も出やすいです。このように、不動産の分け方が一律でないため、相続人間で意見の対立が起こってトラブルにつながります。
こちらも読まれています生前分与とは?生きているうちに相続を検討しておきましょう 「財産なんてほとんどないから、自分には遺産相続なんて関係ない」と思っている方は多いと思います。しかし、遺産相続と無縁な方...この記事を読む
不動産の評価方法でもめる
2つ目に、不動産の評価方法が一律に定まらないことです。不動産は、現金や預貯金などと違い、評価方法が4種類もあるという特殊な資産です。遺産分割の際には、通常「時価」を使いますが、この「時価」がくせ者で、明確な価格をつけることが非常に難しいです。
同じ土地について、同時に複数の不動産業者に査定を依頼したら、数百万円以上の差が発生することも普通にあります。結局、代償金を支払う側は安い方の金額を主張するでしょうし、支払いを受ける側は高い方の金額を主張するでしょう。
さらに、不動産には「相続税路線価」による評価方法もあります。これは、相続税の計算をする際に使う計算方法ですが、遺産相続時にこの評価方法を採用することもあります。これによると、時価より低い価格になるので、支払いをする側にとっては有利です。このように、不動産の評価方法で意見が合わず、遺産相続の際のトラブル要因となります。
こちらも読まれています路線価方式による宅地の評価方法・計算方法のポイントまとめ 相続財産の中に宅地が含まれていれば、宅地の評価額を計算しなければなりません。相続における宅地の評価方法には2種類あります...この記事を読む
相続財産に不動産が含まれていた場合の対処方法
遺産の中に不動産が含まれていたら、どのような対処方法をとれば良いのでしょうか?
この場合、遺言をすることが効果的です。
遺言があると、遺言内容が優先されるので、相続人らが遺産分割の方法を決める必要がありません。たとえば、Aさんのケースでも、親が遺言によって実家の土地建物を長男に相続させることと、ある程度の現金を用意しておいて、次男やAさんが現金やその他の預貯金を相続することを定めておいたら、こんなトラブルになることもなかったし、家を競売にかけられることもなかったのです。
遺産の内容がたった1つの実家の土地建物の場合にこそ、しっかりと相続対策で遺言を残しておくことが大切です。
不動産を相続するときに、してはいけないこと
不動産を相続するとき、してはいけないことがあります。それは、不動産を「とりあえず共有」にしてしまうことです。遺産の中に不動産がある場合、遺産分割協議をするまでの間、不動産は、法定相続人全員の共有状態になります。
持分割合は、法定相続分
そこで、遺産分割協議ができていなくても、共有名義であれば不動産の登記をすることができますし、そのまま放置しておくことも可能です。遺産分割協議をしてもめるくらいなら、共有にしておいたらいいか、と考える例がありますが、このようなことをすると、後でさらなるトラブルの要因になります。
不動産を共有にしておくと、いつかは次の相続が起こる
すると、孫と叔父叔母や、従姉妹同士が不動産を共有することになります。しかも、孫の数は子どもの数より多いので、共有持分がどんどん細分化されて、ものすごい人数の共有持分権者が小さな不動産を共有している状態になってしまいます。こんなとき、売却をしようとしても、お互いにコミュニケーションがとれずに失敗することが多いです。
また、共有持分が細分化されて、一体誰が所有者になっているのかわからなくなってしまうこともあります。
このように、「とりあえず共有」にすると、問題が先送りされるだけで、さらなるトラブル要因になるので辞めましょう。不動産を相続するときには、多少のトラブルがあっても必ず自分たちの世代で解決しておくべきです。
前妻の子どもや認知した子どもが現れる

被相続人に内縁の配偶者がいる場合、被相続人に離婚経験があり、前妻の間に子どもがいるケースや認知した子どもがいる場合にも、問題が起こりやすいです。さっそく、Bさんのケースを見てみましょう。
Bさんのケース
Bさん(50代 男性)は、父母がいますが、このたび、父親が死亡したので遺産相続をすることになりました。相続人はBさんと母親の2人だと思っていたので、半分ずつにすればいいのだから簡単だと思っていたのです。
ところが、相続人調査をすると、父には離婚歴があり、前妻との間に1人子どもがいることがわかりました。もちろん、Bさんが聞いたことのない人です。しかも、父は認知している婚外子も1人いることまで判明しました。
このことは、母も知らなかったようで、大変ショックを受けていました。相続割合は、前妻も認知した子どももBさんも同じなので、Bさんは、遺産をこれらの人たちに渡さないといけません。しかし、遺産の内容は、Bさんの父母とBさんが協力して作ったものがほとんどなので、これらを今まで会ったことのない前妻の子どもや認知した子どもに渡すのは、絶対に納得ができません。
Bさんは、前妻の子どもや認知した子どもに、遺産相続分を放棄してほしいと頼みに行きましたが、2人とも断られてしまいました。「早く法定相続分を、お金でいいからください」と言われて困っています。結局、遺産分割協議ができないので、家庭裁判所で遺産分割調停をして、前妻の子どもや認知した子どもに対し、父の残した預貯金を分与することで解決するしかありませんでした。
認知した子供がいると、なぜもめるのか?
Bさんのケースのように、前妻との子どもや認知した子どもがいると相続トラブルが起こりやすいです。このような場合、相続人同士にほとんど交流がないことが普通ですし、相続開始後初めて判明することもあります。
ただ、今の家族にしてみると、相続財産は、自分たちで形成したと考えているので、これまで無関係だった前妻の子どもや認知した子どもに遺産を渡すことは納得できないのです。これに対し、前妻の子どもや認知された子どもにしてみたら、法定相続分があるのだから、その分はもらえて当たり前だと考えます。
このようなことから、お互いの意見が真っ向から対立してトラブルにつながります。
前妻との子どもや認知した子どもがいる場合の対処方法
前妻との子どもや認知した子どもがいる場合、有効なのはやはり遺言です。遺言によって、今の家族に多くの遺産を残すことを定めておけば、今の家族も納得しやすいですし、他の子どもたちも「遺言があるなら仕方がない」と考えます。
ただ、このとき「遺留分」に注意が必要
前妻の子どもや認知された子どもには、最低限の遺産取得分としての遺留分が認められるので、それを無視して全部の遺産を今の家族に残す遺言をすると、他の子どもたちから「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」をされて、新たなトラブル要因になってしまうからです。遺言をするときには「遺留分」に注意して、それを侵害しない程度の分与割合を定めることがポイントです。
内縁の配偶者がいる

被相続人に内縁の配偶者がいる場合にも、遺産トラブルが起こりやすいです。この場合、内縁の配偶者と今の家族(子ども)が揉め事になります。以下で、Cさんのケースを見てみましょう。
Cさんのケース
Cさんは、もう20年の間、内縁の夫と一緒に暮らしています。戸籍届けをしていないだけで、その他はまったく普通の夫婦と同じように生活していますし、周囲もCさんたちは夫婦だと思っています。Cさんたちが住んでいる家は結婚後に購入したものですが、名義は夫になっています。
ところが最近、夫が亡くなってしまいました。すると、夫の前妻の息子と娘が現れて「あなたには相続権がないので、出ていってください。父のお金も全部返してください」と言われてしまいました。
家はCさんと夫が協力して購入したものなのに、子どもたちのものになってしまうのは納得できません。お金も、Cさんと一緒に積み立てたものです。そこでCさんは、「居住権があるはず」などと主張しましたが、子どもたちはまったく譲りませんでした。
結局Cさんは弁護士に相談をして間に入ってもらい、なんとか納めてもらいましたが、夫名義のお金はほとんど子どもたちにとられましたし、家については、子どもたちに賃料を支払わないといけないことになってしまいました。
内縁の配偶者がいる場合、なぜもめるのか?
内縁の配偶者がいる場合、内縁の配偶者には相続権がないためにトラブルになります。普通の夫婦と同様に生活をしていて財産を共同で積み立てたとしても、その財産は「法定相続人」(先の例では、夫の子どもたち)のものになってしまいます。そこで、法定相続人が権利を主張すると、内縁の配偶者の住む場所すらなくなるおそれがあります。
内縁の配偶者が不利益を受けないための対処方法
このような死後の内縁の配偶者が受ける不利益を避けるためには、やはり「遺言」が大切です。遺言によって、内縁の配偶者に不動産や預貯金などの財産を分与することを定めておけば、内縁の配偶者は住み場所を失うこともありませんし、お金に困ることもないのです。
ただ、この場合にも、法定相続人の遺留分に注意が必要です。最低限、遺留分を侵害しない程度の遺産を残しておかないと、子どもたちが内縁の配偶者に遺留分侵害額請求をして、トラブルにつながるおそれがあります。
親と同居して介護した相続人がいる

親と同居して介護をしていた相続人がいる場合も、相続トラブルが起こりやすいです。Dさんのケースを見てみましょう。
Dさんのケース
Dさんは長女で、長年親と同居していました。母親は身体が不自由になり、介護が必要になりましたが、なるべく自宅で過ごしたいと言うことで、Dさんが献身的に介護をしていました。母親は寝たきりだったため、介護の負担はとても重く、Dさんは働きにも行けませんでしたし、婚期も逃してしまいました。
そんな中、母が亡くなって遺産相続の話が出ました。Dさんには、結婚して家を出ている妹がいましたが、妹は、「法定相続分がある。不動産は要らないから2分の1のお金を払ってほしい。」と言いました。Dさんは、自分は全てを捨てて今まで母親の介護をしてきたのに、結婚して好き勝手に暮らしている妹に同じだけの遺産を渡すことは納得できません。
妹は「同居していたんだから、生活費もお母さんの年金から出しているでしょ?むしろ、得してるじゃないの!」などと言って、遺産分割調停を起こしてきました。
結局、3年もめたあげく、Dさんの寄与分が認められましたが、Dさんが期待していたほどの金額ではなく、法定相続分に少し上乗せしてもらった程度でした。妹とも絶縁状態になりDさんは孤独で、「私の人生は一体何だったんだろう」という思いになりました。
親と同居しているケースで、なぜもめるのか?
親と同居していた相続人がいる場合、その相続人は親の介護をしていたり、親の事業を手伝ったりしていることが多いです。そうすると、自分の遺産取得分を増やしてほしいと考えることが普通です。これに対し、同居していない相続人は「親族なんだから介護は当たり前。生活費を出してもらっているのだから、事業を手伝って当たり前」と考えるので、同居の相続人の法定相続分を増やすことには同意しません。
そこで、お互いの意見が合わずにトラブルになります。
このような場合「寄与分」が認められるかどうかが問題に
介護や事業手伝いの程度が大きければ、特別な貢献があったとして、その相続人の相続分を増やしてもらえることがあります。寄与分を認めてもらうには、最終的に家庭裁判所での審判が必要になるので数年間かかることもありますし、また、いくらの寄与分が認められるかはわからないので、期待していたような結果にならないことも多いです。
親と同居して介護や事業の手伝いをした相続人がいる場合の対処方法
親と同居して介護や事業の手伝いをした相続人がいる場合にも、やはり遺言が役に立ちます。たとえば、遺言によって、同居の相続人の相続分を多くしておけば、相続人らは納得するので遺産トラブルが起こりにくいです。ただしこの場合、同居していない相続人の遺留分を侵害しないように注意する必要はあります。
また、親として、同居していた相続人に寄与分を認めるほどの貢献はないと考えるなら、法定相続分通りに分割する内容の遺言にしておけば良いのです。どちらにしても、きちんと遺言があれば、子どもたちも納得がしやすいです。
こちらも読まれています寄与分とは?長年の介護・看護など相続分の増額が認められる条件や計算方法を解説 寄与分とは被相続人の介護や生活支援、事業の支援などでお世話したり、支えたりした場合には、法定相続分よりも多く相続財産を受...この記事を読む
子どもがいない夫婦

子どもがいない夫婦の場合、法定相続人が少ないので遺産トラブルが起こりにくいと思われるかもしれませんが、実は意外とトラブルが起こりやすい類型です。以下で、トラブルになったEさんのケースを見てみましょう。
Eさんのケース
Eさんは、夫と2人暮らしで、子どもはありません。お互いに初婚で前妻や前夫などの子どももなく、相続は単純だと思っていたので、遺言を用意することもありませんでした。
そうこうしているうちに、夫が亡くなってしまいました。夫の両親は早く亡くなっていて、夫の兄も以前に亡くなっていたため、Eさんは、自分が相続人になるものだと考えていましたが、夫の兄の子ども(夫の姪)2人が現れて、「私たちが相続人になる」と言ってきたのです。
Eさんは驚きましたが、代襲相続ということで、この場合Eさんと姪2人が遺産を分け合わないといけないことがわかりました。今まで夫の姪などほとんど会ったこともなかったので、Eさんは納得できない思いでしたが、法律的な権利があるということで、Eさんは姪2人に遺産を渡さざるを得ませんでした。夫と2人で積み立てた財産をどうして姪に渡さないといけないのか、Eさんは今でも納得できない気持ちを抱いています。
子どもがいない夫婦の場合、なぜもめるのか?
子どもがいない夫婦の場合、法定相続人同士のかかわりが薄いことが多くなります。子どもがいないと、第2順位の法定相続人である親が相続をします。すると、配偶者と親が相続をすることになりますが、このとき、配偶者と親のそりが合わない場合などには、相続がトラブルのきっかけになってしまいます。
たとえば、もともと嫁姑問題があった場合などには、相続したら夫の遺産を嫁と姑が取り合うことになるので、争いは激しくなります。
親が既に亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人となるので、配偶者と兄弟姉妹が共同相続人となります。この場合にも、もともとの関係がうまくいっていなかったらトラブルになりますし、もともと疎遠であるケースも多く、スムーズに遺産分割を進めにくいです。
さらに、兄弟姉妹が先に亡くなっていたら、Eさんのように、代襲相続によって兄弟姉妹の子どもたちが共同相続人になりますが、そうすると、生前ほとんど関わりのなかった甥や姪に遺産を渡さないといけなくなり、配偶者としては納得できない思いになります。
子どもがいない夫婦が遺産トラブルを避ける対処方法
子どもがいない夫婦が遺産トラブルを避けるためにも、やはり遺言が有効です。この場合、配偶者に対して遺産を残す内容の遺言をすれば良いのです。ただ、親には遺留分があるので、親の遺留分を侵害しない内容にしておく必要があります。
兄弟姉妹やその甥姪(代襲相続人)には遺留分がないので、妻と兄弟姉妹(甥姪)が相続人になる場合には、遺産の全部を妻に分与する内容としても問題ありません。
こちらも読まれています代襲相続とは?起こる要因と相続人になる人の範囲・相続割合 相続が起こったとき、本来の相続人が被相続人より先に死亡していたら「代襲相続」が起こるケースがあります。代襲相続はどのよう...この記事を読む
事業承継が問題になる
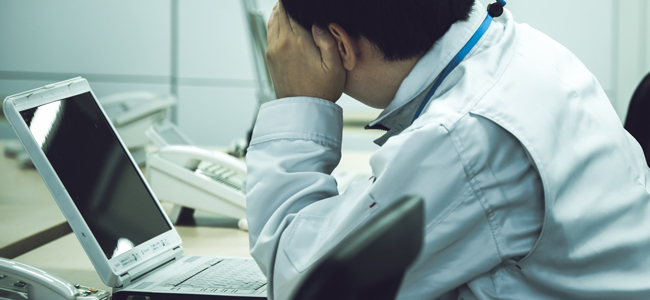
遺産トラブルが起こりやすいパターンとして、事業承継が問題になるケースもあります。
事業承継とは、被相続人何らかの事業を営んでいて、その事業を特定の相続人に承継させる場合です。この場合、事業を承継する相続人と、それ以外の相続人との間でトラブルが起こりやすいです。被相続人が、個人事業者であった場合でも、法人の経営者であった場合でも、どちらでも問題になります。
Fさんのケース
Fさん(50代 男性)の父親は、若い頃に会社を設立して、長年経営者としてひた走ってきた人でした。会社は大きくなり、多くの従業員もかかえていて、近隣の県にも支社を出していますし、不動産などの資産もそれなりあります。ところが、ワンマン経営者であった父親が亡くなってしまったため、会社はパニック状態になってしまいました。
もともとFさんが引き継ぐはずでしたが、会社の仕事の引継ぎも受けていませんでしたし、遺産相続問題についても全く考えていなかったのです。父親には個人資産もありましたが、会社に関係する資産も多く、特に会社の株式はほとんどが父親が所有しています。
Fさんが会社を承継するので、他の相続人である兄弟に対し、「僕が会社を継ぐから、株式と会社関係の資産は僕がもらってもいいよね?」と言うと、兄弟は「別にいいけど、代償金を支払ってほしい」と言ってきました。そこでDさんが公認会計士に依頼して株式の評価をしてもらったら、驚くほどの高額な評価がついてしまったのです。
Dさんは、そんなお金は到底支払えないと思い、兄弟にそのことを言うと「それだけ価値のあるものをもらうんだから、支払をして当然だ。借金してでも支払え」と言ってきました。また、父親には会社関係の借入もありましたが、兄弟は「借金も平等に相続するんだから、プラスの資産も平等にするのが当然だろ?」と言いました。
結局、遺産トラブルが起こって会社経営が滞り、会社の業績が落ちて大きな損失が発生しました。何とか倒産は免れましたが、支社はたたんで本社のみを残し、資産も売却して会社の規模を縮小しました。その上で、評価の下がった株式の分、兄弟に代償金を支払って何とか遺産相続を済ませました。父が生きていた頃とはまったく様相が変わってしまった会社を経営しながら、Fさんは、他にもっと良い方法があったのではないか?と感じています。
事業承継でなぜもめるのか?
事業承継が絡むと、単なる遺産相続だけではなく、会社や事業の承継の問題も発生するので、同時に調整をしなければなりません。事業関係の資産があることも多いため、単純に法定相続分で分けることには問題があります。事業用の資産を法定相続分で分けると、事業の継続ができなくなってしまいます。
そうなると、事業承継する相続人が相続するしかありませんが、事業用資産や非公開株式の評価が高額になると、それらについての代償金が高額になって、支払えなくなります。
遺産トラブルが長引くと、その分事業自体の経営が放置されて、業績が悪化したり倒産したりすることもあります。Fさんのように、結局資産を売却して事業を縮小せざるを得ないケースも起こってきます。
事業承継での相続トラブル対処方法
事業承継が絡む場合に遺産トラブルを避けるためには、被相続人の生前から事業の承継を行っておくことが重要です。亡くなるまで被相続人がワンマン経営をしていたら、相続開始後会社を運営することができなくなって、会社経営が滞ってしまうからです。
遺産については遺言を残しておくことが非常に重要
事業を承継する相続人には事業承継に関する資産を集中させなければなりません。それ以外の相続人については、なるべく事業に関係のない預貯金などの資産を選び、遺留分相当の遺産だけを渡すようにすると良いです。また、事業を承継する承継人に生前贈与をする方法も効果的です。このように、事業の継続と遺産相続の両面からきちんと対策をしておけば、難しいと言われる事業承継も、恐れることはありません。
遺言で相続トラブルを防止するなら弁護士相談を!
以上のように、遺産相続でトラブルになるパターンはいくつもありますが、どのケースにおいても「遺言」が重要なキーポイントとなります。効果的な内容の遺言を残しておくと、多くの遺産トラブルは予防することができるのです。ただ、兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分」が認められるので、遺言をするときには遺留分を侵害しないよう、注意が必要です。
また、事業承継の際などには、事業自体の承継と財産相続の両面から生前贈与を活用しつつ、効果的な遺言内容を検討しなければなりません。このようなことは、素人判断では難しいので、法律のプロである弁護士に依頼すべきです。遺言によって相続トラブルを防止したいなら、まずは弁護士に相談しましょう。
遺産相続に強く評判の良い弁護士事務所を探す
遺産相続不平等な遺言がある
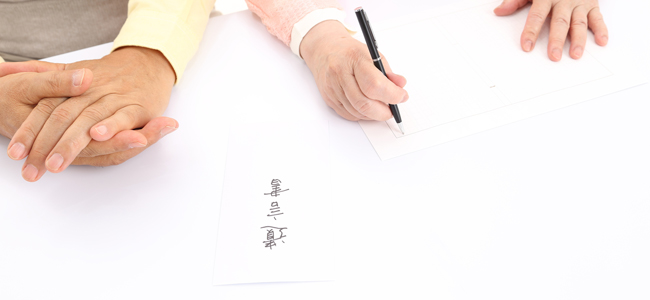
今まで、遺言があると相続トラブルを避けやすいという説明をしてきましたが、遺言があっても必ずしも問題を予防できるとは限りません。むしろ、遺言がトラブル原因になることがあるので、注意が必要です。以下では、遺言がもとで遺産争いが長期化したGさんの事例を見てみましょう。
Gさんのケース
Gさん(60代 女性)は、3人兄弟の末っ子です。先日、母親が亡くなったために、兄弟4人が相続をすることになりました。遺言を見ると、母親は長男に遺産の大部分である実家の土地建物を分与することにしていて、弟とGさんには、100万円程度の預貯金しか残さない内容となっていました。Gさんと弟はショックを受け、しばらく悩んでいたのですが、やはり納得ができないので、遺留分侵害額請求をすることにしました。
兄に対し、遺留分侵害額請求の通知書を送ると、兄は逆上して、「非常識だ。母親の遺志に背くのか?」などと言ってきましたが、Gさんも後に引けないので、遺留分侵害額請求を起こして、話合いをしました。調停委員の説得もあって、遺留分に該当する800万円を支払ってもらうことができましたが、Gさんと兄は、その後絶縁状態になってしまいました。
法事も一切一緒にすることがなく、年賀状のやり取りすらしなくなりました。Gさんは、お金をもらえたことには納得していますが、兄と交流がなくなったことについては残念で、遺留分侵害額請求をしたことがよかったのかどうか、正直なところよくわからない思いです。
不平等な遺言で、なぜもめるのか?
Gさんのように、不平等な遺言があると相続トラブルになります。それは、兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分」があるためです。
遺言によって遺留分を侵害すると、遺留分の権利者は遺留分侵害額請求を行い遺留分に相当する金銭の返還を求めることで、かえって遺産トラブルの原因になってしまうのです。遺留分侵害額請求が起こると、お互いに感情的な対立が発生して解決しづらくなり、遺留分侵害額調停や、ときには遺留分侵害額訴訟が起こり、長期間の争いに発展することも多いです。
遺言トラブルの対処方法
遺言によってトラブルを予防したいなら、遺留分を侵害しない内容にすべきです。たとえば、Gさんの例では、母親が兄に不動産を残すとき、ある程度の現金資産も用意しておいて、Gさんと弟にも十分な価格の現金や預貯金などの別の資産を残しておいたら、遺留分侵害が発生せず、トラブルを防ぐことができました。
遺産の中に不動産しかない場合には、生前に不動産を売却することも1つの方法ですし、どうしても特定の相続人に多くの遺産を相続させたい場合には、生前贈与を利用することをおすすめします。たとえば、居住用の不動産を長男に生前贈与しておいたら、それは遺産分割の対象にならないので、長男が確実に取得することができます。
こちらも読まれています遺留分とは?遺留分の仕組みと弁護士に依頼するメリットを徹底解説 遺言や贈与があると、本来の法定相続人であっても遺産相続ができなくなることがありますが、そのようなとき、遺留分侵害額請求(...この記事を読む
第三者に対する遺贈をする遺言がある

遺言によって発生するトラブルとしては、第三者に対する遺贈をする内容になっているケースも多いです。たとえば、愛人や介護してくれた人など、親族でない人に高額な遺産を分与してしまうケースです。以下で、Hさんのトラブル事例を見てみましょう。
Hさんのケース
Hさん(60代 女性)は、長年連れ添った夫がいましたが、このたび夫が亡くなったため、遺産相続問題が起こりました。普通に考えるとHさんと息子が相続するものだったので、息子と話し合って相続の手続きを進めようとすると、家の中から遺言書が出てきたのです。
そしてそれは、ある女性にほとんどの遺産を分与する内容となっていました。その女性は、夫の愛人の女性だったようです。Hさんは、愛人のことも知らなかった上、遺産まで愛人にとられることとなり、大変なショックで寝込んでしまいました。
しかし、そうも言っていられないので、愛人に「遺産を放棄してほしい」と言いに行きましたが、愛人は「全部受けとります」と言って譲らず、家の登記まですべて愛人名義にされてしまいました。Hさんと息子は、愛人に対し遺留分侵害額請求をすることに決めて、家庭裁判所で遺留分侵害額の請求調停を行いました。
その結果、Hさんと息子は、自宅の不動産を返してもらうことになりましたが、遺留分だけでは不動産の価値に及ばなかったので、不足額の500万円を愛人に払わなければなりませんでした。その他の預貯金や株式などは全部愛人にとられました。Hさんと息子は、なぜこんな目に遭わなければならないのかと、理不尽に感じています。
第三者への遺贈はなぜもめるのか?
第三者に遺贈をする遺言をすると、法定相続人との間でトラブルになります。特に法定相続人の遺留分を侵害していたら、ほとんど確実に遺留分侵害額請求が起こされるでしょう。
このケースを見てもわかるとおり、法定相続人にしてみると、親族でもない人に遺産が分け与えられるのは耐えがたいと感じますし、遺産を受けとる方にしてみると、これまで自分が被相続人の介護をしてきたとか、支えになってきたなどの思いがあるので、やはり譲らず、激しい争いに発展してしまいます。
第三者に対して遺贈をするときの対処方法
第三者に対して遺贈をするときには、余り極端な分与をしないことをおすすめします。少なくとも、法定相続人の遺留分は侵害すべきではありません。いくら愛人やお世話になった人がいるとしても、家族にもそれなりに面倒をかけてきたはずですし、残された家族の思いにも配慮をしましょう。たとえば、家族と一緒に住んでいる家などは、愛人やその他の人に分与すべきではありません。
どうしても愛人などに残したい大きな財産があるなら、それは生前贈与しておくと、遺産の対象から外れるので遺産トラブルを避けることができます。
こちらも読まれています遺贈と贈与の違いとは?メリット・デメリットについて解説 お世話になったこの人に財産を与えたい、あの人にはこの財産を受け取ってほしい、という希望を叶える方法として「遺贈」と「死因...この記事を読む
遺言が偽物だと言われる
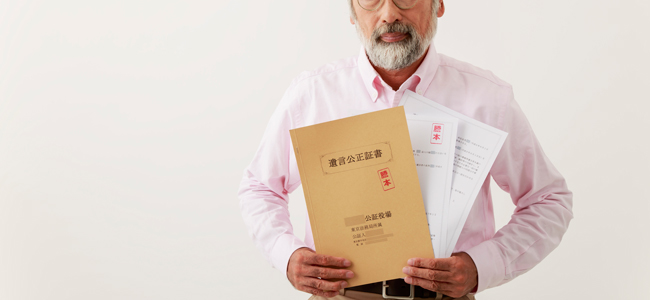
遺言が原因でトラブルになるケースとして、遺言が偽物ではないかと言われるパターンがあります。これは、自筆証書遺言の場合に特に多いです。以下で、Iさんのケースを見てみましょう。
こちらも読まれています自筆証書遺言の書き方マニュアル~遺言書の例文ひな形と準備・作成のポイント 自筆証書遺言は、他の2つの遺言(公正証書遺言・秘密証書遺言)と違って証人が不要です。費用もかからないため一番多く利用され...この記事を読む
Iさんのケース
Iさん(60代 男性)は、4人兄弟の3番目で、全員男兄弟です。先日父親が亡くなったので遺産分けをしようとしたところ、父親の遺言が見つかりました。中を見てみると、長男と次男に半分ずつ、Iさんと弟には何もなし、という内容になっていたのです。
長男は父と同居していましたし、次男は長男と仲が良いので、Iさんと弟は、兄たちが結託して遺言書を偽造したのではないか?と考えました。考えてみたら、父親は晩年弱っていて遺言を書く気力などなさそうでしたし、物忘れもひどくなっていて、認知症になっていたような様子もあったので、遺言をできる状態ではなかったとも思えます。
Iさんと弟は筆跡鑑定などを行い、兄のところへ持っていって、「筆跡も違うし、遺言は偽物。ちゃんと4分の1ずつの遺産を渡してほしい」と言いました。すると、兄たちは逆上して「偽物のはずがない。遺産は渡さない」と言い、別の筆跡鑑定をして、本物だと主張してきたのです。
Iさんと弟は、どうしても納得ができないので、兄たちに対し、遺言無効確認訴訟を起こしました。この結果、遺言書は偽物であるということになったため、Iさんたちは遺産分割協議を開始しましたが、すでに兄弟関係が酷く悪化しているためまったく話合いになりません。
そこで、家庭裁判所で遺産分割調停をして、ようやく遺産分けが完了したのは父が亡くなってから5年後のことでした。これだけ苦労をして、得られた遺産は1000万円です。Iさんは、弟とは交流がありますが、上の2人の兄とは絶縁状態ですし、今後一生、一切の関わりを持ちたくないと考えています。
遺言の真偽でなぜもめるのか?
遺言があっても、それが偽物だと疑われたら、かえって相続トラブルの要因になります。遺言が偽物ではないかと疑われるのは、その遺言が自筆証書遺言で、どのような状況で作成されたかがわからないためです。遺言の真正が明らかにならない場合、自分に不利になっている相続人は、「遺言書が無効」と主張しますし、自分にとって有利な内容になっている相続人は「遺言書が有効」と主張するので、争いになります。
この場合、遺産分割に関する争いではないので、遺言無効確認調停や遺言無効確認訴訟という裁判手続きが必要です。そして、遺言が無効ということになれば、それを前提に遺産分割協議をしなければならないので、遺産トラブルが非常に長引きます。
遺言が偽物だと言わないための対処方法
遺言が偽物だと言われてトラブルになるのを防ぐには、信用出来る方法で遺言書を作成しておくべきです。
有効なのは、公正証書遺言の作成
公正証書遺言とは、公証役場で公正証書としての遺言書を作成してもらう方法ですが、公正証書遺言は、公証人が法律に従った適式な方法で作成するものなので、無効になることが非常に少ないです。また、きちんと身分確認をした上で作成するので、偽造の心配も要りません。
遺言をするときには、手間がかかっても公正証書遺言の形をとるようにしましょう。いったんは自宅で自筆証書遺言を作成しても、その後その内容を公正証書にしておくことをおすすめします。
こちらも読まれています公正証書遺言とは?作成方法や費用について詳しく解説 自分の土地や財産を愛した人に与えたい、家族に相続問題で悩んでほしくない、そんな思いを込める遺言書が書き方や保管の問題で「...この記事を読む
遺言が実行されない
遺言書があってもトラブルになるパターンとして、遺言内容が実行されずに放置されるパターンがあります。Jさんのケースを見てみましょう。
Jさんのケース
Jさんは、父親を早くに亡くしていて母と2人暮らしでしたが、最近、父方の祖父が亡くなったという連絡を受けました。Jさんは、ほとんど祖父とはかかわりがなかったのですが、遺言によってJさんにも不動産や預貯金の分与が行われていました。
ただ、Jさんは現役世代で忙しく、不動産の登記や預貯金の払い戻しなどをする暇がなかったので、何もせずに放置していました。そうこうしていると、いつの間にか、不動産がJさんと叔父(父の兄)の共有名義で登記されていたのです。しかも、叔父の持分は、まったく別の第三者に売却されたとも聞きました。また、銀行預金は、叔父の法定相続分だけ、払い戻されてしまいました。
Jさんは驚いて、これはすべて自分の財産だと主張しましたが、買い受けた人は「そんな事情は知らない。〇〇さん(叔父)の名義になっているのだから、それを信じて当然だ」と言って持分を返してくれません。Jさんは、裁判をして争い、何とか持分を返してもらうことができましたが、そのために1年以上の期間と労力と費用がかかりました。
Jさんは、こんなことならすぐに遺言書によって相続手続きをしておけば良かったと思っています。
トラブル要因は?
遺言があっても、遺産を受け継ぐ人が必ずしもきちんと遺産相続の手続きをするとは限りません。Jさんのように、相続登記も預貯金の払い戻しもせずに放置してしまう人もいます。登記をせずに放置していると、Jさんの叔父のように勝手に共有登記にしてしまう人がいますし、第三者に売却されてしまうこともあります。
預貯金は、法定相続分だけ下ろされてしまう可能性もあるのです。いったん登記や払い戻しが行われたら、取り戻すのは相当大変です。特に第三者への売却が行われた場合、裁判で負けたら不動産の一部を第三者にとられたままになってしまうおそれがあります。
対処方法
遺言内容が実行されないリスクを予防するためには、「遺言執行者」をつけておくことをおすすめします。遺言執行者とは、遺言内容を実現する役割を負った人のことです。具体的には、不動産を相続した人の名義に登記名義を換えたり、預貯金の払い戻しを受けて相続人に渡したり、株式の名義変更をしたり、寄付をしたりします。
遺言執行者を選任しておくと、その人が不動産の相続登記や預貯金の払い戻し、株式の名義変更などの具体的な遺産相続の手続きをしてくれるので、相続人は何もしなくてよくなります。また、遺言が自分に不利な内容になっている場合、遺言内容の実現に消極的な相続人もいますが、遺言執行者がいたら、相続人が協力しなくても相続手続きができるのでスムーズに進みます。
さらに、遺言によって認知をする場合や相続人の廃除、取消をする場合、相続人にはできないので、必ず遺言執行者を選任しなければなりません。
Jさんのケースでも、遺言執行者がいたらその人がJさん名義に不動産の登記名義を変更してくれて、預貯金の払い戻しと送金をしてくれたはずなので、トラブルになることはありませんでした。
遺言執行者を選任するなら、弁護士を選ぼう
遺言執行者は、遺言によって指定することができますが、その際、誰を指定すべきかも問題です。このとき、特定の相続人を指定すると、他の相続人がその相続人に対して不信感を持つので、遺言がスムーズに実現されないおそれがあります。
そこで、遺言執行者としては、公正な第三者である弁護士を指定すべきです。弁護士は、法的知識が豊富なので、相続手続きや認知、相続人の廃除などの各種の手続きをスムーズに進めることができますし、トラブルの解決能力が高いので、相続人間で何らかのトラブルが起こったり、手続きに非協力的な相続人がいたりしても上手に対処することができます。
こちらも読まれています遺言執行者(遺言執行人)とは?務める役割と必要なケース、メリット・デメリットまで解説 自分の死後、遺言書の内容を円滑に実現できるよう動いてもらうのが遺言執行者の役割です。本記事では、遺言の実現のため相続手続...この記事を読む
遺言書を作成するなら弁護士に相談しましょう
以上のように、遺言書を作成しても、遺言書がかえってトラブル要因になってしまうことが多いです。遺言によって法定相続人の遺留分を侵害してしまうこともありますし、自筆証書遺言を作成した場合などには相続人から「遺言書が偽者」と言われてしまうこともあるためです。遺言書による相続トラブルを避けるためには、遺言書の内容や作成方法にも配慮しなければなりません。よく「遺言書があると、相続トラブル予防になる」と言われているため「とりあえず遺言書を作ろうかなぁ」と考える人もいるでしょうけれど、自己判断で適当な遺言書を作成したら逆効果です。
そこで、遺言書を作成する際には、必ず法律のプロである弁護士に相談しましょう。弁護士であれば、法定相続人の遺留分にも留意しながら、関係者全員が納得しやすく、かつ被相続人の希望を実現できるような、バランスの良い内容の遺言内容を提案してくれます。また、弁護士を遺言執行者に指定しておけば、スムーズに遺言内容を実現できて、相続人に手間をかけることもありませんし、余計なトラブルを招くことも防ぐことができます。
遺言書の問題だけではなく、すでに相続が起こった後のスムーズな解決方法を知りたい場合、相続トラブルが起こってしまって困っている場合でも、弁護士の助けを借りることが有効です。
トラブルなしに相続を終わらせたい場合には、まずは一度、遺産問題に強い弁護士に相談しましょう。
遺産相続に強く評判の良い弁護士事務所を探す
遺産相続この記事が役に立ったら
いいね!をお願いします
最新情報をお届けします
相続問題で悩みを抱えていませんか
- 相手がすでに弁護士に依頼している
- 遺産分割の話し合いがまとまらない
- 遺産を使い込まれているがどうすれば?


