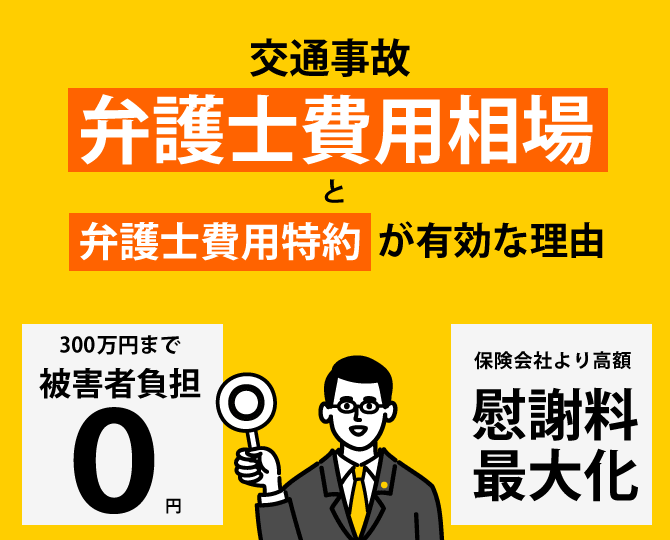交通事故加害者への処罰。起訴されても略式命令に終わる可能性も
- 監修記事
-

佐藤 學(元裁判官、元公証人、元法科大学院教授)

交通事故の加害者に対する処罰は、統計的に見ても、必ず厳罰が科されるとは言えない状況です。
加害者の起訴(公訴提起)は、被害者など私人が行うことはできず、公訴権を持っているのは検察官だけです。
重大事故においては、当然公判の裁判が行われ厳罰が科せられますが、「加害者に謝罪の意思がない」とか「誠意が見られない」という理由だけでは、被害者の望む刑罰が加害者に科されるとは限りません。
目次[非表示]
刑事手続きにおいて起訴されても、加害者に重い罰が下るとは限らない
交通事故に遭ってしまい、事故以前の生活や仕事が失われてしまったり、不便を強いられたりすることになった被害者の感情としては、損害賠償だけではなく、加害者に重い刑事罰を望むこともあるでしょう。
特に、損害賠償のお金だけで片付けてしまい、謝罪の気持ちも示さず、悔悟の念も全く感じられない加害者に対して、強い処罰感情が沸き上がるのは当然のことです。
多くのケースでは略式手続きで終わる
しかし、実際の刑事手続きでは、加害者がひき逃げをした、あるいは飲酒運転をした末に事故を起こしたなど、よほど悪質な違反をして事故を起こしていない場合は、比較的甘い処分で終わってしまうケースがよくあります。
処分の甘いケースが多いのは
- 交通事故の加害者が、故意に事故を起こしたわけではない
- 損害賠償金や慰謝料の支払いを含めて民事的な解決がすでに終わる(あるいはその予定である)
などがその理由となっています。
また、被害者に対する損害賠償金や慰謝料を支払うためには、加害者に一般社会の中で、きちんと仕事をしてもらわなければならないこともあり、総合的に判断して刑罰は罰金のみに落ち着くことが多いのが実情です。
交通事故の加害者に対する刑事手続きがどのようなものかを見てみましょう。
起訴されても略式手続きで罰金のみ
交通事故の加害者が、刑事手続きにおいて起訴されることは少ないとされています。
令和2年版犯罪白書(令和元年の検察統計年報)によれば、過失運転致死傷等の人員37万0,910について、起訴総数4万4,805、うち公判請求4,806(全体の1.3%)、略式命令請求3万9,999(全体の10.8%)、不起訴31万6,255(全体の85.2%。起訴猶予30万5,808、その他1万0,447)、家庭裁判所送致9,850(全体の2.7%)となっています。
このように、起訴されたとしても、略式命令請求が多く、その請求を受けて、必然裁判所も略式命令を発することになり、略式な手続きだけで終了してしまうことが多いのが実情です。
下記で略式手続きを詳しく見てみましょう。
正式な裁判なし・書面審理のみの略式手続き
加害者(被疑者)に科せられる刑罰が罰金のみの場合、検察官の判断で正式な裁判のための公判請求はせず、書面審理のみで裁判(略式命令をする略式手続きが行われることがあります。
この略式手続きが可能なのは、加害者に100万円以下の罰金又は科料が科せられると見込まれる事件の場合に限られます。
交通事故の場合ですと、加害者が逮捕されない在宅捜査になることが多いので、手続きがゆっくり進むことが多いのも特徴です。
略式命令の請求は、以下の流れで行われます。
- 検察官が、加害者に出頭を求め、起訴前に加害者に対し略式手続きの内容について説明する
- 通常の手続きで審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続きによることに異議がないかどうかを確認する
- 加害者作成の異議がないことを示す書面を起訴状に添付する
- 証拠書類・証拠物とともに簡易裁判所に提出する
請求を受けた簡易裁判所は、書面審理のみで判断し、請求のあった日から14日以内に略式命令を発し、略式命令書の謄本を加害者(被告人)に送達します。
ただし、以下のような事由があるときは、職権で通常の公判手続きに回さなければなりません。
- 略式命令のできない場合(例えば、罰金・科料の定めのない事件)
- 検察官が略式手続きの説明を怠ったり、同意書を添付していない場合及び裁判所が公開の法廷で審理することが相当であると認めた場合(例えば、事案が複雑であるとき、証人調べを必要と考えるとき)
略式手続きが終了したら、事件の処理は終了
略式手続きが終了してしまったら、加害者への刑罰は罰金程度じゃ納得できないと被害者が考えても、どうにもなりません。
被害者に謝意も示さず、反省の色も感じられない加害者に科せられた刑罰が、100万円以下の罰金程度では生ぬるいと思う被害者は当然いるでしょう。
しかし、略式命令が発せられ、仮納付の裁判があった場合は、直ちにその裁判を執行して加害者に罰金を仮納付させれば、本当に当該事件(交通事故の刑事手続き)は終わりです。
一事不再理というルール
その理由は、日本の刑事訴訟法上で、特定の刑事事件について有罪あるいは無罪の判決、又は免訴の判決が言い渡されて確定した場合、同一の事件について再び公訴を提起することができないという、一事不再理というルールがあるためです。
簡単に言えば、刑事訴訟においては裁判で判決が確定した事件を、もう一度審理することはできないということです。
略式手続きは、裁判を省略した刑事手続きですが、そこで発せられた略式命令は、普通に裁判を行って審理した結果言い渡された判決と同じものになります。
そのため、略式命令の内容が、被害者にとって納得のいかない軽いものであっても、同じ事件で同じ加害者を告発することはできないのです。
刑事訴訟では被告人にも検察官にも上訴権が認められる
刑事訴訟においては、公訴権は検察官にしかありません。
検察官は、刑事手続きにおいて、十分な捜査を行い、被疑者を有罪とできる証拠が揃ったと判断して公訴を提起(起訴)するのです。
しかし、言い渡された判決に不服がある場合は、被告人のみならず、検察官も上訴(控訴・上告)することができます。
なお、略式命令に不服がある場合は、被告人も、検察官も、正式裁判の申立てをすることができます。
実際の裁判が行われるのはどういうケース?
前述の通り、交通事故においてはすべての事故において刑事裁判が行われることはありません。
そして起訴され刑事手続きが進められるとしても、略式手続きで終了してしまうケースが多いのが実情です。
実際の裁判が行われるケースは?
一方で、ひき逃げ事件はもちろん、飲酒運転、過度なスピード違反などで重大な交通事故を起こした場合には、懲役や禁錮が言い渡される可能性が高いため、公判が開かれる可能性が高いと言えます。
公判で有罪の判決が言い渡されれば、一生消えない前科がつきます。
懲役や禁錮の実刑判決が言い渡されたならば、刑務所で長い時間を過ごすことになるのです。
厳罰化の傾向が強まる交通事故の処罰
悪質、重大な事故については起訴され刑事裁判が行われますが、近年、交通事故の加害者に対しては厳罰化の傾向が強まっていることに注目が集まっています。
2013(平成25)年、自動車運転死傷処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)が成立し、翌年5月20日からに施行されています。
それ以前は、刑法に規定されている危険運転致死傷罪、自動車運転過失致死傷罪とされていましたが、刑法上の規定を削除し、自動車運転死傷処罰法は、刑法の規定を移す形をとるとともに、新たな規定を設けて整理したものです。
過失運転致死傷罪(5条)では、7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金が科せられます。
また、より悪質な運転による事故については危険運転致死傷罪(2条)では、
- 人を負傷させた者は15年以下の懲役
- 人を死亡させた者は1年以上の有期懲役
危険運転致死傷罪(3条)では、
- 人を負傷させた者は12年以下の懲役
- 人を死亡させた者は15年以下の懲役
が、それぞれ科せられます。
危険運転致死傷罪(2条、3条)の場合には、略式手続きで行われることなく、公判によって加害者に刑罰が科せられます。
早めに全力で動くことが重要
刑事手続きにおいては、検察官が略式命令を請求する前に、全力で動くしかありません。
略式手続きが行われる前、被疑者(交通事故の加害者)を公判の法廷で裁判を受けさせるには、検察官が略式命令を請求する前に、上申書などを送ったり、直接担当検察官に面会を求めたりして、被害者の立場から加害者の公判請求を訴えることが必要となります。
弁護士の力を借りて、できることはすべて行うこと
一般的な刑事事件で被疑者が逮捕された場合、事件の内容によっては、身柄拘束中のまま、略式命令の謄本が被告人に送達された時に釈放手続きがとられます。
しかし、幸いにも、多くの交通事故の場合は、在宅捜査となりますので、刑事手続きはそれほど迅速には進みません。
交通死亡事故でも、略式命令の請求まで1年近くかかった例もあるようです。
加害者に対して強い処罰感情を抱いている場合、刑事手続きがまだ進んでいなければ、検察官に公判請求を願い出るという方法があります。
しかし、加害者を罰したいという処罰感情だけでは、検察官は動いてくれません。
弁護士の力を借りて、法律的に正しい方法で訴えるしかありません。
交通事故に強い【おすすめ】の弁護士に相談
交通事故一人で悩まずご相談を
- 保険会社の慰謝料提示額に納得がいかない
- 交通事故を起こした相手や保険会社とのやりとりに疲れた
- 交通事故が原因のケガ治療を相談したい